2900話:時間との競争・ノヴァの下の救出劇
2900話あらすじ、3回目である。
気づいたら、ほぼ4章構成の原書どおりの進行になっている(笑)
明日明後日は仕事の都合上不在にするので、最終回(予定)は、たぶん日曜じゅうには、どうにか(^^;
これまでのお話:
■ごやてん:>2900話:怪奇! 水星の地下に謎のレムール兵馬俑を見た!!(爆
■ごやてん:>2900話:莫迦には見えない新星!? 灯火は点された!
ホントはもう1つ記事はさむつもりであったのだが……連続アップだと、必要ないなココw
(承前)
司令室のパノラマ・ギャラリーに映るのは、中間空間のゆらめくもや。その中でただひとつ輝いているのは――目標星。タルターンである。リニア空間を移動しながら見えるものが即現実とイコールなわけではないが、ゆらめき、脈動するその様子は、恒星が極度に不安定であることを実感させた。
そして、通常空間への突破の瞬間、スクリーンをそれまでとは異なるゆらぎと輝きが満たした。警報サイレン。パラトロン・バリアが展開される。
《ラス・ツバイ》は荒ぶる恒星が吐き出した熱波と高温のガスに呑み込まれつつある惑星系に飛び込んだのだ。
第一惑星は熔鉄のかたまりにしか見えない。駐在していた科学者2名がどうなったのか、現段階では判断がつかなかった。
一方、かつては広大な極冠を有し、大きな大陸のない多島世界であった第2惑星マンダームでも、混沌が渦巻いていた。海は一部蒸発し、昼の側の植物相は炎上している。悪天候に阻害され、被害状況の確認もままならない。
《ラス・ツバイ》発進前に連盟から発された要請を受け、近隣にあった宇宙船が官民を問わず近傍宙域に集まっていたが、彼らにはこの極限状況で救助活動をおこなうだけのキャパシティが足りない。
ホロンダーの号令一下、惑星周回軌道に入った《ツバイ》から8隻のマーズ級巡洋戦艦が分離し、惑星各所へ散っていく。司令室のホロ・グローブには、そこからさらに射出された搭載艇が降下していく様子が見てとれた。
本来残留組であったパイロットのカントヴァイネンも、ただ見ているだけの状況に耐えられず、志願してスペース・ジェットの1機を指揮して出動する。嵐の雲間を抜けたジェットが目の前にしたのは荒れ狂う海であった。一部の海水の蒸発に伴い、海流すら変わっている。もし出航していた船があったとしても、望みはあるまい。
おそらく津波に襲われたのだろう、海岸部も目に映るのは岩と泥ばかり。ジェットは逆流する波に洗われた谷と丘を越え、内陸部へと飛んだ。
ようやく発見した村……かつて村であったらしい、倒壊家屋の集まりで、捜索活動が開始される。
「残された時間がどのくらいかわからない。長々と論議しているヒマはない。いざとなったら……コレだ」
カントヴァイネンは、麻痺モードにセットされたコンビ銃を示した。うなずくあと5名。おいおい(笑)
#結果的に、(このチームは)使わないで済んだよーだがw
ゾンデが瓦礫の中の空洞や温度を走査し、可能性のある場所でロボットが木材石材を撤去する。やがて、ようやく、ある敷物の下に探知された空間から、ほっそりした4本指の手がのびているのが発見された。青い肌はほこりにまみれている。カントヴァイネンは、安心させようと、その手をそっと握りしめた。
救出されたマンダーム人は、青紫の肌をもつ、無毛のヒューマノイドだった。身長およそ3m。身体も四肢もおそろしく細い。
(ニョロニョロ? いや、こんなん動画サイトで見たぞ……棒人間!?)
ただし、棒人間には背中に羽など生えていないのだが(ぁ
2時間後、カントヴァイネンたちが汗みどろになって救出したマンダーム人はやっと18名。運良く生き埋めになっていなかった者は、大半が近隣の街へ救援を求めにむかったらしい。
避難をうながすテラナーたちだが、そもそも運命論者的なこの種族、異人への疑念が捨てきれないらしい。この事態を引き起こしたのがオレたちじゃないって、ホントにわかってもらえてるんだろうか……(汗)
状況が好転したのは、村はずれにあった残骸の地下から、ひとりの少年――といっても、身長2.5mで、カントヴァイネンよりはるかに背が高いのだが――を救出してからだった。
「変な服着てるね! 星から来たの? エペチュアンのヒト? ジャリクイの巻物には、エペチュアン人は鋼鉄のシリンダーを大砲から撃ち出して宇宙を飛ぶって書いてあったけど。こんな小さいとは思わなかったな!」
このテーラー君、好奇心旺盛で10歳の少年にしては知識豊富だが、イロイロと偏っているご様子(笑) 初めて読んだ本(巻物)がSFもしくはトンデモ本だったようで、以来ずっと宇宙へいってみたかったんだとか。
ともあれ、テーラーがカントヴァイネンの言葉を信じ、受け入れてくれたことで、他の村人たちとの関係もぐっと改善された。スペース・ジェットは道――の名残――沿いに飛行し、街へとむかった者たちをも順次回収してから、母艦への帰途についた。
「星は? 空のむこうには星があるんじゃないの? それとも、あれは空に貼り付けてあっただけなの?」
「いまここは明るすぎて見えないだけだよ。もっと大きな船に着いたら見せてあげよう」
「ん? これが大きな船じゃないの?」
「いやいや、一番小さいやつさ。これならマンダームのあちこちで同時に人を収容できるからね。これから、まず母船へ帰って、それからもっと大きな船に戻るんだ。こいつはもう空飛ぶ都市でね、いろんな種族、総勢35000人が生活している」
「へーえー?」
疑ってる疑ってる(笑)
《ラス・ツバイ》へと帰還したカントヴァイネンは、テーラーを連れて司令室へむかった。ローダン、シクさんとの打ち合わせがちょうど一段落したらしい艦長に、直談判して曰く――
テーラーは、惑星の反対側にあるコミューンから、いとこの元へ預けられていたらしい。上階にいたであろういとこの一家は全員消息不明。惑星の裏側にいた家族は言うにおよばずである。テーラーは孤児となったのだ。
そして、マンダーム人の間では、コミューンの異なる孤児を受け入れることは稀であるそうで、実際、あの村で他に救助された面々は、テラから来た救援艦隊へとすでにまとまって収容済みである。
テーラー自身はよるべのない身となったことを、わりと淡々と受け入れていた。ボク、科学者になりたかったんだ。でも、コミューンの手伝いをしなきゃいけないからって……だけど、もうコミューン自体がなくなったのなら、ひょっとしたら、ボクでも科学者になれるかな?
そう語ったマンダームの少年は、いま、「クニで最高の科学者」と紹介されたシクさんと楽しそうに言葉をかわしている。
さて、そこで本題。
「飼っていいでしょ。ボクがちゃんと世話するから」
「ダメです。元の場所へもどしてきなさい!」
……とは、ならなかった(爆)
艦長は苦笑して、テーラーを被保護者にするというパイロットの要望を承認した。
カントヴァイネンは、笑わない男であった。どうしてか、無理矢理そうしているような表情になるせいだった。自分の顔は、笑うようにできていないのだ。そう思っていた。
なのに、なぜだろう。テーラーと話していると、笑みがこぼれるのだった。
マンダームにおける救助活動の時間を稼ぐため、シクさん立案の〈ネット〉作戦が開始された。疎開したマンダーム人に、できうる限り住み慣れた環境を再現するためには、多数の動物・植物をも収容したいところでもある。
恒星タルターンのマンダームに面する位置に、複数の電磁場を展開し、噴出する高熱ガスをそらそうというものだ。同時に、惑星各所にパラトロン・バリアを設置する。
不安定な恒星近傍での危険な作業であり、実際、起動直前にタルターンが吐き出した熱波のため、第1層を構成するゾンデの半数が破壊されるというトラブルも生じたが、カントヴァイネンら作戦に従事する者たちはひるむことなく働きつづけ、〈ネット〉は作動をはじめた。これで、《ラス・ツバイ》でなくとも後続の船団が救援活動を続行できる状態が整った。
一方、その頃。
ブルー人の科学者ユスリュユンは、座席にもたれ鼻歌を歌っていた(ブルー人に鼻の穴はないかもしれないが)。
彼の主導するプロジェクト、〈無限の昏き獣の深き目〉が、その本領を発揮すべき時が訪れたのだ。
要請は、自由ギャラクティカー連盟主席と、なおユスリュユンをやる気にさせることに、サン計画担当連盟コミッショナー、すなわちペリー・ローダンの連名で届いたもの。
ローダンの唱える種族の協調……ユスリュユンのような科学者にとって、国境とか紛争とか、実に噴飯物である。力を合わせることによって、不可能も可能となるというのに。
ちょうど、彼の〈深き目〉のように。
〈無限の昏き獣の深き目〉は、銀河系各所の天文台を連動させることによる、深宇宙の探査プロジェクトである。様々な波長の可視光、電磁波、ハイパー・スペクトル……無数の天文台で観測されたそれらデータを、ハイパー波の同期通信で結び、彼のもとにあるポジトロニクスに集約する。
探すべきものがあれば、〈深き目〉は必ず見いだすであろう。
新星化したオテルマのせいで、ソル系からケンタウルス座方向の観測は、現在、事実上不可能だ。しかし、銀河系の他所に複数の視点を持つ〈深き目〉にとっては、何の問題もない。
水星上空に生じた〈灯火〉の指し示す方角に、いったい何があるのか――。細工は流々、後は待つだけである。
静かな部屋に、ユスリュユンの――人類には機械的補助なしでは聞くことのできない――鼻歌が、悠々と流れ続けた。
(続く)
■Wikipedia:棒人間
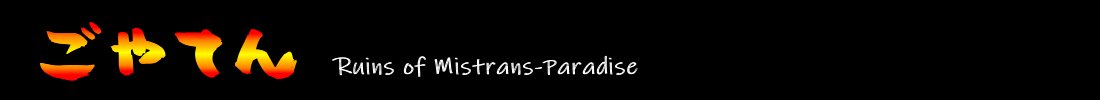


ディスカッション
コメント一覧
テーラー少年、まるでローダンの子供時代みたいですねw
同類ですね(笑)
まあ、1000話を見た限りでは、ペリー少年ここまでグイグイくる感じはしないんですけどw
無限艦隊サイクルの「ケース・マウンテンの少年」を読むと、またイメージ変わりそうな気もします(未読ですが(^^;)